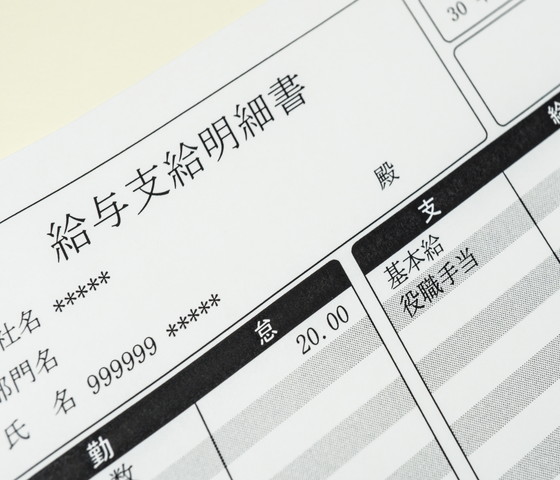給料のキャッシュレス化
しあさっての11月23日は、言わずと知れた「勤労感謝の日」。「勤労を尊び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」という趣旨の元、今から70年前の1948年に国民の祝日として制定されたそうです。
この祝日は、「働いている人々に感謝の気持ちを伝える日」。つまり私のような働くお父さん他に対し「ありがとう」を伝える日であると幼少のころから教えられてきたような気がしていましたが、よくよく調べてみると・・・11月23日という日は元々は「新嘗祭(にいなめさい)」と呼ばれる祭日で、天皇が日本国民を代表し、五穀豊穣とそれに対する神への感謝を捧げるための祭りの日だったのだそうです。ところが戦後、日本国民から、天皇や皇室に関係したものを徹底的に切り離そうとしたGHQの手により新嘗祭は解体。代わりに「勤労感謝の日」という祭日が出来上がったとのことです。元々は収穫をお祝いする日だったのですね。
ところで「勤労」、すなわち働くことについて、その目的は人それぞれですが、多くの人の主目的に「給料を得ること」があるかと思います。最近はその給料の受取り方法にも変化が起きようとしています。先日、次のような新聞報道がありました。
「企業が従業員に支払う給与について、厚生労働省が電子マネーでの支払いも可能とするよう規制を見直す方向で検討を進めていることが24日、同省関係者への取材で分かった。プリペイドカードや、スマートフォンの資金決済アプリなどに企業が入金する仕組みが想定される。国内で進むキャッシュレス化に対応する狙い。」
労働基準法第二十四条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており、現行法の下では、電子マネー等での支払いは認められていません。そこに規制緩和を図り、お金の流れを多様化しようという狙いです。受け取る側は、銀行からお金を引き出す手間が減って便利になりますが、金融機関にとってみると、大きなインパクトありそうです。例えばひとり10万円のお給料を毎月貰っていると仮定すると、日本の就業者は6,000万人超と言われていますから、ざっと6兆円を超えるお金が毎月、どこかの銀行口座に一旦は振り込まれていることになります。これが本規制緩和でそっくり無くなってしまい、直接、交通系や流通系の企業に持っていかれることになります。また、給料を引き出す必要がなくなれば、銀行の支店やATMに足を運ぶ人の数は激減することでしょう。
解決しなければならない課題が多すぎて、簡単には実施できないと個人的には思っていますが、金融機関の将来像を考えるには十分な内容の記事。20年以上も前からビル・ゲイツは「将来、銀行は必要なくなる」と唱えていましたが、その日がすこしづつ近づいているのでしょうか。
ところで冒頭で書いたように、私は今日までずっと、この祝日を「働いている人々に感謝の気持ちを伝える日」と信じて疑わず、それにも関わらず毎年、ひと言も感謝を伝えてこない家族に対して怒りすら感じていましたが、このコラムを書く中で納得できました。勤労感謝の日は、感謝を伝える日ではないのですから、それで良いのですね。
(田中記)